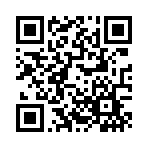2024年10月21日
真の改革者
「聖域なき構造改革」 をたびたび口にする小泉首相も、いよいよ化けの皮が剥げてきた。
改革は、もちろん賛成であり、道路公団をはじめとする公共団体のぬるま湯体質が、徐々に明らかになってきたことは、大いに歓迎である。
ところで、世の中には、変えなくてはいけないもの、変えてはいけないものがあります。絶対変えてはいけない、手を触れてはいけない分野を聖域と称します。
絶対守るべきものが聖域であり、その守るべきものが明確にわかっている人が、真の改革者です。
小泉首相は、 「皇室典範に関する有識者会議」 の報告書が公表された、直後の記者会見で 「いわば皇室の構造改革ですね」 と言っている。
郵政民営化等々の改革と、同じレベルで捉えていることに、これは歴史への冒瀆といわなければならない。
次回から、その見証を試みたいと思います。
Posted by 中川知博 at
08:00
│Comments(0)
2024年10月07日
親を思う
中国の古典『礼記』の中に、子供は両親にどのように接すればよいか、その手順を次のように述べています。
両親の居間に参上したとき———
1) 心を平静にし、やさしい声で、着物が暑すぎないか、寒すぎないか、たずねる。
2) 痛むところ、かゆいところはないか、たずねる。痛むところは押え、かゆいところは、かいてさしあげる。
3) 両親がその部屋から出る時は、先に立ったり、後ろに回ったりして、支える。
4) 洗面用のたらいを勧める時は、若い者が水を捨てるバケツを、年上のものが水を捧げてゆく。終わったら、手ぬぐいをさしだす。
5) 朝食はなにがよいかたずねる。朝食をうやうやしく、顔色をやわらげて、すすめる。
(『新行儀読本』 河出文庫より)
時代や環境は異なっていても、親あるいはお年寄りに対しての、やさしい、思いやりの仕草が述べられているのではないでしょうか。万分の一でも見習いたいものです。
Posted by 中川知博 at
08:00
│Comments(0)
2024年09月16日
日本のよさを見てもらおう
アメリカの学生が、初めて日本にやって来て、どんな感想を抱いたか新聞に載っていたので紹介したい。
2週間の半分は、アパートに泊まり東京で過し、後の1週間はユースホステルんい泊り、京都・奈良のお寺を訪ね、自由な旅を満喫したようだ。
東京では、多くのタクシーにカーナビがついていて、若者を刺激する最先端の技術にふれ感心する一方、お店でもレストランでも、日本語が話せないアメリカ学生に、非常に親切に接してくれた心の温かさに感激したといいます。
また、京都や奈良の古いお寺や、関西の美しい自然も心を打たれたようです。米国にはない、古い日本の文化の前に尊敬の心をもったようです。
日本人も忘れがちな日本のよき文化に、彼らはいたく感激して、また遠からず来たいと言っています。
年若いうちに異国の文化に触れることは、非常によいことです。こうして一個人としての国民が、他国民と交際する機会をもつことが、国同志が理解するためにも必要なことです。やがて、世界に平和をもたらす基礎になる気がします。
(2月25日 朝日新聞より)
Posted by 中川知博 at
08:00
│Comments(0)
2024年09月02日
慈愛の心
作家の村上龍さんは、高校生時代は警察にもお世話になる不良少年であったそうです。その後、家を逃げるように東京へと旅立ちます。
一週間ほどたった頃、彼のもとに父親から一通の手紙が届きました。その内容は、家族のようす、近所の出来事など身近なことが書かれていました。彼を非難することは、何ひとつありませんでした。
そのまま読み捨てていたが、翌週も、翌週も、故郷のようすがさりげなく書かれたハガキが届きました。返事を一度も書かなかったが、七年間にわたって2千通にもなったそうです。
親の立場からすると、つい説教がましくこうしろあゝしろと叱ったり、責める気持になるところですが、淡々と粘り強く、子供をあくまでも信頼しようとする父親からの、慈愛の心が感じとれる。
対立や誤解から、お互いの心が離れてしまった場合、何とか説得しようとして、こちらが頑なになればなろほど、相手は身構えてしまい、聞く耳を持とうとしないものです。相手を変えるのは、つきせぬ慈愛の心なのです。
Posted by 中川知博 at
08:00
│Comments(0)
2024年08月19日
子供の躾
70歳の老人が、昔を振り返って次のようなお話をされた。
「私たちの子供の頃は、悪いこともしたが、人を傷つけることはしなかった。せいぜい、畑や庭の野菜や果物を、失敬したぐらいだ。友達と喧嘩をしても、コブを作った程度やった。第一、親や先生が恐いものだから、子供なりに良くわきまえていた。近所のおじさんやおばさんからも、悪いことをすれば、怒られた。こうして社会のルールや、人間関係について学び、子供として何か一本筋が通っていた気がする」
さて、最近の子育てはどうでしょう。私は、躾をするという事が全く解ってない様な気がする。
先日も、うどん屋さんに、4人の子ずれの若いお母さんたちが昼食をとっていた。その時の子供たちのやかましいこと。一言も叱りもせず、ほったらかしであった。これでは、社会のルールなど守れるはずがない。公の場では、他の人に迷惑のかからないように、言って聞かせるのが躾である。
叱ると怒るは本質的に違う。子供は、ほったらかしにしておくと、何でもOKという気になって育ってしまう。
躾とは、制限を加えてやることである。やってはいけないこと、我慢すること、しなければいけないことを、子供の将来のために、本気で叱らなければならない。親の意にはまらない時や、腹がたって理性の伴わない怒りは、何の効果もない。
Posted by 中川知博 at
08:00
│Comments(0)
2024年08月05日
自分との戦い
幸せを得ようとするならば、それに値する努力をしなければなりません。それは、他人との戦いではなく、自分自身の感情 (心)、論理 (理性) との戦いです。
他人の心を変えようなんて思うことは、とうてい無理なことです。まずは、自分から変わることです。そのほうが早くて確実です。
修練女の経験のあるノートルダム清心学園理事長の渡辺和子さんは、次のように語っています。
草むしりをしているとき、修練長から 「あなた達は、草を毟(むし)っているだけだ。草を根こそぎ取らないと、またすぐ生えてきますよ」 続けて、 「悪の道に入ってしまい、そこから足を抜こうにも抜けない青年がいっぱいいるのですよ。その人達のために祈りを込めて、草を根こそぎ抜いたらどうですか」 と言われた。
そこで次のように思ったそうです。
「自分が変わることによって、それまではつまらないとしか思えなかった仕事が、意味ある仕事に変わり、私は修道院の片隅にいても、他人のために生きる幸せ者になりました。」
人を変えようとするよりも、渡辺さんの体験も、彼女の態度 (心) の他に変わったものは何もなかったのです。
他人の心を変えようなんて思うことは、とうてい無理なことです。まずは、自分から変わることです。そのほうが早くて確実です。
修練女の経験のあるノートルダム清心学園理事長の渡辺和子さんは、次のように語っています。
草むしりをしているとき、修練長から 「あなた達は、草を毟(むし)っているだけだ。草を根こそぎ取らないと、またすぐ生えてきますよ」 続けて、 「悪の道に入ってしまい、そこから足を抜こうにも抜けない青年がいっぱいいるのですよ。その人達のために祈りを込めて、草を根こそぎ抜いたらどうですか」 と言われた。
そこで次のように思ったそうです。
「自分が変わることによって、それまではつまらないとしか思えなかった仕事が、意味ある仕事に変わり、私は修道院の片隅にいても、他人のために生きる幸せ者になりました。」
人を変えようとするよりも、渡辺さんの体験も、彼女の態度 (心) の他に変わったものは何もなかったのです。
Posted by 中川知博 at
08:00
│Comments(0)
2024年07月15日
寛大な心
もしあなたが、誰かに期待した微笑が返ってこなかったら、不愉快になる代わりに、むしろあなたの方から、微笑返してください。
実際、微笑を忘れた人ほど、あなたからのそれを、必要としている人はいないのですから。
人はちょっとしたシグナルの損で傷つきますが、そのキズを癒す最良の薬は「仕返し」ではなくて 「許しと愛」 なのです。相手への思いやりに基く、寛大な心でしかありません。
人は多くの癖を持っています。性格も違いますし、ましてやいい癖や悪い癖、いい性格や悪い性格とさまざまです。特に、悪い癖や性格を補い合うことが、人間関係・・・・・・例えば夫婦の間・・・・・・・の上で大切です。
受け入れて、許す心がなかったら、相手に返すだけです。寛大な心は、自分にも他人にも幸せをもたらす 「気づかい」 なのです。
Posted by 中川知博 at
08:00
│Comments(0)
2024年07月01日
「いいこと」は他人との関係から生まれる
私たちは、人間関係の中で生活しています。自分だけをプラスの状態にしておいても、他人との関係をマイナスにしておいては、ドアを閉じた状態ですから 「いいこと」 は起こってきません。
「いいこと」は、他者との関係から起こるのです。昔から、いつも多くさんのお客さんが来る家は、幸せも訪れると言われます。同じことなのでしょうね。
心はいつもプラス (嬉しい・楽しいなど) の状態にしておくこと。なぜなら、心の状態そっくりに、現実をつくるという法則があるからです。
他人に対しても心 (大切に思う) と、行動 (手助けをする) の面で、プラスにしておかねばなりません。
自他ともに、常にプラスの状態にしておくと、 「いいこと」 が起こります。
Posted by 中川知博 at
08:00
│Comments(0)
2024年06月17日
スポーツ選手の脱プレッシャー
トリノオリンピックで、最後の最後にようやくアイススケートの荒川選手が、金メダルに輝いた。4年に一度の祭典は、一発勝負という怖さがある。日本人の弱点は、実力がありながら、ここ一番に弱いきらいがある。プレッシャーに弱いのだろうか。
体調の維持、国民の期待を背負い、選手にしかわからない、自分との戦いがあるのだろう。女子レスリングの浜口京子選手が、プレッシャーに打ち勝つ手立てが、新聞に載っていた。
(朝日新聞 2月19日)
彼女はほぼ毎日日記をつけている。又、海外の試合へ出発する時には、必ず家族全員に手紙を書くのだそうだ。 「手紙を書くと、迷いとか不安が消える」 と、彼女は言っている。 「私が選手の中で一番練習した」 「努力したんだから、私は優勝する」 「向こうで待っている。私のことを一生懸命応援してね」 とかが書いてある。
「やることはやったと、気持ちをすっきりさせる。これをやらないと日本を出発できない」 と言っている。
手紙の効用は、あらかじめ筋道を立てて書くため、口で言うより漏れることがない。その上、文字の響きもあり五感にふれて相手に伝わる。そしていつまでも残る。
浜口さんは、 ”やるだけのことはやった” と、自分に言い聞かせ、迷いを断ち切ろうとしているのだろう。
Posted by 中川知博 at
08:00
│Comments(0)
2024年06月03日
幸福な人と不幸な人
不幸な人は、心が満たされていないために
1) さみしく、イライラしているのが最大の特徴です
2) 愚痴や悪口、泣き言が多く
3) 人を褒めることよりも、人を批判することの方が多い
4) 自慢話しが多く
5) 人に何かしてもらっても、なかなか満足できない
6) 悪いことは人のせい、良いことは自分がやったという発想をする (被害者意識が強い)
7) 人から裏切られたと感じることが多い
8) 嫉妬深い
幸福な人は、イライラすることも少なく、人と楽しくつきあっています。悪いのは自分のせい、良いことは自分以外のおかげと、常に感謝して生きている人です。
不幸な人は実は、自称幸福者なのです。自分は不幸でないと思っています。自分を幸福にしてもらおうと、無意識に強く願っています。幸福になれないのは、誰も自分のために働いてくれないからだと、人のせいにします。
世間の人は冷たい。幸福な人は、運がいいだけ、世の中は不公平だと、いつも不平不満ばかり言っています。
幸せは、自分の手で努力してつかむものです。ところが、自分のためにするのではなく、 「人の幸せを願う」 という逆の発想なのです。
Posted by 中川知博 at
08:00
│Comments(0)